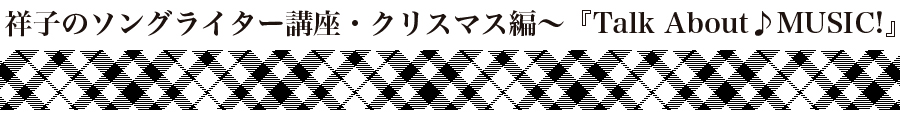第3回『超・個人的音楽史~その1』
美しいなあ、日本って美しい。
そんな言葉が心の底から出てきたのは初めての経験でした。自分の声がエコーのように胸に残りました。
このあいだまで緑のにおいでむせかえるようだった木々が赤や黄色に色づいて、腰の高さほどもあった夏草は枯れ、窓の向こうにはすすきが揺れる晩秋の風景です。
淡いピンクの夕映えに山のシルエットが浮かび上がる夕暮れを眺めていたらその言葉がふっと、歌みたいに口をついて出て自分でもびっくりしました。
ソングライター講座も3回目なので、ここでちょっと個人的な話をしてもいいでしょうか?
思えば私は西洋の音楽――洋楽から音の世界に惹かれていった人間でした。最初は祖父の書斎にあったレコードを遊びのようにひっくり返して聴いたクラシック、教会で歌ったこども讃美歌。
初めて“ポップス”と恋に落ちる想いをしたのは当時大人気だったベイ・シティ・ローラーズの『バイバイ・ベイビー』。中学に上がってテキサスに行って、ラジオから毎日流れてきたのはジャーニーやフォリナーのアメリカン・ロックでした。
高校に上がった春から夢中で観ていた小林克也さんの『ベストヒット・USA』。高2の秋に初めて聴いたビートルズの『アビー・ロード』、原宿のペニーレインに通った冬。衝撃的だったジョン・レノンの『ジョンの魂』。
何だか遠~い目の想い出モードに入っていますが、一般に最も感受性がつよいと言われる時代、つらつらと思いだしてみても私の中心にはいつも、いつでも洋楽が在ったわけです。
レコードに合わせて歌ううちにカセットに録った声を別のカセットに録りながら歌う多重録音(?)を思いつきました。ビートルズの『ベイビーズ・イン・ブラック』をこっちのラジカセに向かって歌って、それを聴きながら下のパートを別のデッキで録って再生するとあら不思議!独りで二声のハモりが出来上がります。
それを誰に聴かせるでもなく独りで再生して悦に入っていたことを思い出すと、48の今と何ら変わらないと云いますか、三つ子の魂百までと申しますか、独り多重録音好きの芽はこの頃に芽生えていたのかと思います。
歌うのは好きでしたし聖子ちゃんや明菜ちゃんの写真を持って美容院に行ったりはしましたが、歌手になりたいと云う思いは全くありませんでした。私はドラマーになりたかったし、師匠の藤井章司さんのようにアーティストのバックで演奏するバッキング・ミュージシャンになりたかったのです。
それが何の間違いかシンガー&ソングライターになる羽目に陥って、初めて聴かせてもらったのはキャロル・キングとジェイムス・テイラーでした。
「最高のものから盗め。」
―STEAL FROM THE BEST.
コッポラ監督の言葉です。誠に至言だと思います。シンガー&ソングライターというものになった途端ベストの中のベスト、その言葉のオリジネイターであり意味そのもの、であるひとたちを聴かされてしまったのだからたまりません。
ジェイムス・テイラーの伝記の中に忘れられない言葉があります。「1960年代のアメリカで成長するということの痛みを、彼ほど真摯に歌い、分かち合ってくれた存在は居なかった。」
長年のファンの述懐です。シンガー&ソングライターとはそういうものかと心を打たれました。
キャロル・キングは御存知のように、かの『タぺストリー』に至る以前1960年代からジェリー・ゴフィンとのコンビでヒットを量産してきた筋金入りの「ソングライター」です。Singer&Songwriterという名称の真ん中にある“&”は「シンガー」であるより前に「ソングライター」であること、歌を、音楽を「書く人」であるということを物語っているように感じられました。
どこまでも「個」であること、そして「音楽的」であること。――自分自身にもう一度、その意味を問い直したいと思う今日この頃なのであります。
第2回『チェンバロ、クラヴィコード、フォルテピアノ、ピアノ、そしてウーリッツァー~17世紀から20世紀、歴史を旅する鍵盤楽器~その3』
アメリカ・ウーリッツァー社の電気ピアノ(Electronic Piano)は1954年に初めて造られ1955年に発売されたそうです。
創業は1934年、パイプオルガンの製作からスタートし、その後自動オルガンや電子オルガン、ジュークボックスのメーカーとしても名を馳せました。
アコースティック・ピアノも製作していたウーリッツァー社はグランドピアノのアクションのしくみを利用し、金属製のリードを叩いて発音、電気的に増幅する電気ピアノを作り出しました。ロックやポップの世界ではウーリッツァー、という社名が楽器の名前として定着してしまったということなのですね。
ライブに足を運んでくださったことのある方にはおそらくお馴染みのわたしのウーリッツァーは多分Classroom106 Beige というモデル。文字通り学校の音楽教育用に作られた、と聞いたことがあります。
ウーリッツァーと並ぶヒストリカルな二大電気ピアノと云えばフェンダー・ローズですが、あの楽器も元々は精神療法のために作られた歴史があるそうです。ふたつの電気ピアノの共通点は特徴的なトレモロ効果。
確かにあの独特のトレモロは神経を沈静化し、心を落ち着かせる効果があると感じます。トレモロの深さや幅をシンプルなつまみで調整出来るのも魅力です。因みに私の目盛りはいつも8~10の最深です(笑)。
ウーリッツァーの電気ピアノは1982年まで製造され1984年まで販売されていました。いま手に入れようと思うとモデルにも依りますが25万~30万円になるのでしょうか。
ウーリッツァーの特徴は金属製のリードがもたらすシャープなアタックと、それと相反するような転がるように軽く、柔らかな響きだと思います。フェンダー・ローズは音の減衰が非常に長いためウーリッツァーほど明快なアタックが出ませんが、楽器そのものの大きさもあってより深みのある響きです。
私はどちらも大好きですが、演奏していてウーリッツァーは「明るくて可愛い」フェンダー・ローズは「内面的で大人っぽい」と感じます。
バッハの時代より前のクラヴィコード、チェンバロからベートーベンの愛したフォルテピアノ、現代のモダンピアノ、そしてエレクトリカルに音を増幅した電気ピアノ。鍵盤楽器の歴史を駆け足で振り返って来ましたがいかがでしたでしょうか?
全部の楽器に触れて、弾いて感じることはそれぞれの「時代の必要性」、その止まらない流れと相反するように「音を求める心」は何百年経っても変わらない、ということです。
今はプロツールスのプラグインですべての鍵盤楽器のサンプリング音が手軽に再現出来る時代ですが、それもまた"より短時間で、より合理的に"という時代の必要性です。
しかし楽器を目の前にしてふたを開け、鍵盤に触り、楽器全体の重みや響きを身体で感じることは他に換えられない素晴らしい体験だとも思うのです。
そのどちらも必然であり、人間が自由に選べば良いのだと思いますが、音は最初の打撃と響きの余韻、それを包む空気が影響を与えあって出来ているというのを生理的に"識る"ことはとても大事だと感じます。
時代の必要性と時代を超えた必然性、それをどのように両立させてゆくのか。。。音楽に限らず今私たちが考えるべき大きな課題なのではないでしょうか。
一丁前にデビュー25周年なんて言っていますが、鍵盤楽器の歴史や製作家の心にまで思いを馳せたのはやはり現代の素晴らしい製作家との出逢いがあったからだと思います。その技術の高さと「音」に対する感性を心から尊敬するとともに、自分も人と、良い音と出逢いながらまだまだ成長してゆけたら、と心から思いました。
P・S
この記事を書くに当たり久保田彰さんと深町研太さんにお話をうかがいました。本当に有り難うございました。
第2回『チェンバロ、クラヴィコード、フォルテピアノ、ピアノ、そしてウーリッツァー~17世紀から20世紀、歴史を旅する鍵盤楽器~その2』
その時代の楽器製作家は何を目指していたんでしょうか?という私の質問にいや、たまたまですよ、こういう素晴らしい理想があって夢があって、って云うのは後の時代の人間が勝手に言ってるだけなんじゃないかな、必死にやってたらたまたまそうなった、ってことだと思うんですね。
と深町さん。楽器の音色や外見の美しさに幻惑されて、こんなものを造る人はいったいどんな夢を描いていたんだろう、と思ってしまうのですね。
人間とか、人生といったものはシジフォスの神話を引くまでもなく元々が「無理」なものだと思うときがあります。
無理と云うのはあれが出来ないこれが嫌い、の無理ではなくて、も少し正確に言うと存在、は抜き難い不可能性のうえに辛くも成り立っていて、必死でない人も不安でない人もこの世には居ない、
"自己実現"だの"自己啓発"を考えるより寧ろこの不可能性について考えるべきなのじゃないか、――などと思うことがあります。
バッハだってモーツァルトだって生前は散々な目にばかり遇って、なんでこんな凄い人が?理解出来ない!と思うのがきっと「後の時代の人間が勝手に言ってること」なのです。
時代を追って聴いていくとわかるのですが、バッハもモーツァルトも物凄く、物凄~く独特です。剣呑、といって良いくらい「行き過ぎて」いる。
名曲、偉人、天才、そんな呼び名なんて本当にその後の人間の後出しジャンケンに過ぎません。あれをリアルタイムで聴いたらきっと凄くびっくりします。何か、概念がちがうんだもの。
音楽は夢のように美しく泡のように儚く、星のように輝き。。。そんなふうに思ってる人にあんなもの聴かせたってなんじゃこりゃあ!と思うだけです、きっと。
バッハの厳格な対位法のなかにある何とも云えない悩ましさや懊脳って何なのか?と考えると「神」という概念に突き当たらずにいられません。あんなに「人間」に肉薄した音楽を人々は聴いたことがなかったでしょう。
モーツァルトだって何だか"星のように輝く"美しい先人たちをからかって揶揄してるみたいな時があります。そんな諧謔味のなかに何かゾッとする殺気があって、あんなもの聴かされたってやっぱりなんじゃこりゃあ!だったと思うのです。
同時代の人たちを必要以上に弁護するわけではないけれど、そう考えると作曲家たちも楽器製作家たちも皆必死で、不安のなかで書き、考え、作っていたんだと云うことがわかります。
第二回のタイトルでもある「鍵盤楽器」というのは元々イタリア名で
クラヴィチェンバロ
と呼びならわされるものだったそうです。フランス名の「クラヴサン」は「クラヴ=サンバル」、なるほどイタリア語読みでは「クラヴィチェンバロ」です。
いまピアノ、ピアノと普通に呼ばれている楽器の正式な名前は「ピアノフォルテ」。これは私でも知っていました(p・fと表記することもあるもんね。)でも何故「ピアノフォルテ」なのでしょう。
それはチェンバロには無かった「強弱がつけられる」という画期的な特性のためなのだそうです。現在のモダンピアノの前身、昨日までわたしの目の前にあったフォルテピアノの正式名は
クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ
長っ!つまり弱と強のあるクラヴィチェンバロ、と云う意味なんですね。ピアノフォルテと云うのは現代的、便宜的ないいかたなのだそうです。し、知らなかった。。。
この「強弱がつけられる」という最大の武器によって、チェンバロが廃れ消えてしまうくらいの人気を博したのがフォルテピアノ、だったのですね。
いま目の前にある「クラヴィコード」はチェンバロの前からある楽器で、教会のオルガン奏者が自宅での練習や研鑽のために弾くことが非常に多かったそうです。
ピアノよりチェンバロよりオルガンより小さな音量、しかしこの楽器の内面的な表現力は素晴らしく、モーツァルトはクラヴィコードを使って『魔笛』を書いたそうです。
楽器と云うよりまるで自分自身の一部のように、心と直接繋がって一体になる。クラヴィコードの響きとは本来そういうものだそうです。
クラヴィコードを目の前にしながら「~だそうです。」なんて云うのは、私がまだクラヴィコードの本当の響きに全然届いていないからなのです。ーーいつか自分の内面と繋がっているような一体感、を感じることが出来るのでしょうか?
長くなってごめんなさい。続きはまた!